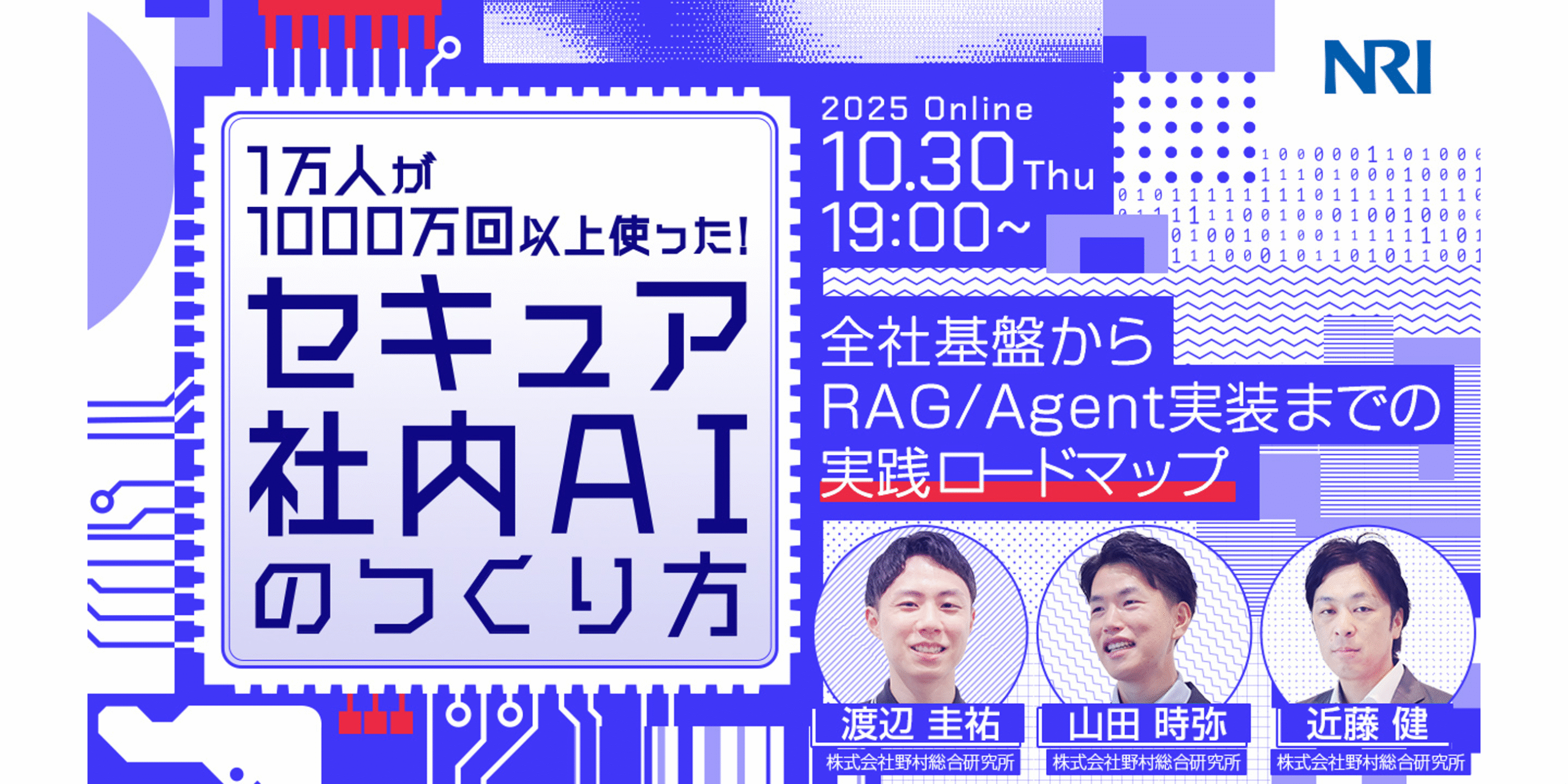キャリア入社者が早期に活躍する組織の秘訣とは「キャリア入社者のプロアクティブ行動」×「情報がオープンで心理的安全性の高い組織」
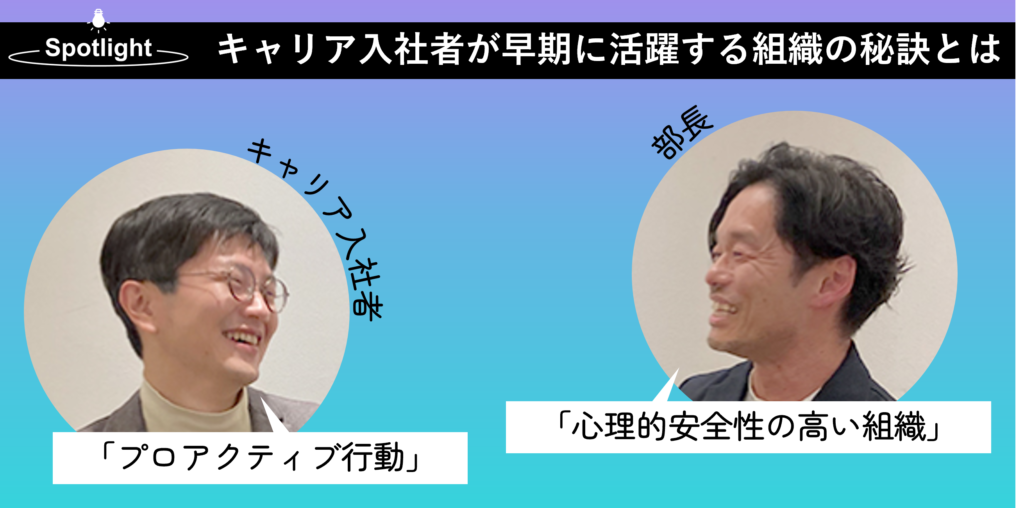
キャリア入社者が早期に活躍できるために
野村総合研究所のキャリア採用サイト「NRI career」をご覧いただきありがとうございます。
「Spotlight」はNRIで活躍する多彩なメンバーに光を当て、それぞれの仕事に対する想いやNRIで働く魅力をお伝えしていくシリーズです。
NRIグループへのご応募を検討いただいている方の中には「NRIの仕事に馴染めるのだろうか」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そんなみなさまに入社後のイメージをより具体的に持っていただけるよう、今回、通信・サービスソリューション事業本部の部長である和田研一さんと、2021年にキャリア入社した坂田宏樹さんにインタビューを行いました。
和田さんが心掛けている「キャリア入社者が活躍しやすい組織運営」や、坂田さんが仕事を進める上で意識している主体的・積極的なコミュニケーション(プロアクティブ行動)がなぜ重要なのか、というポイントを実体験を交えつつ語ってもらいました。
話し手:通信・サービスソリューション事業本部 部長 和田 研一さん、坂田 宏樹さん
注)組織名・役職名は取材当時の名称です。
キャリア入社者がキャッチアップしきれない「暗黙知」をなくすために
―― まずは和田さんにお聞きします。坂田さんが配属される以前の組織状況や和田さんのマネジメントに関する考え方などを教えてください
和田:私は坂田さんがNRIに入社する前になりますが、かなり大規模なプロジェクトの推進を担当していました。当時、NRIデジタルから20名ほどの支援メンバーに入ってもらいながらなんとか納期を守ることはできましたが、何よりもメンバー各自のパフォーマンスを引き出すことができなかったことに強い悔いが残りました。
当時の支援メンバーの多くは、数年前の坂田さんのように、NRIに入ってきたばかりのキャリア入社の社員がほとんどでした。なぜ、彼らのパフォーマンスを最大限に引き出せなかったのかについて、私なりにいろいろと考えてみたところ、NRIのプロジェクトや業務には、キャリア入社の社員たちが早期にキャッチアップしきれないような「暗黙知」的な情報・ノウハウが存在しており、それらがオープンになっていなかったことが原因だったという結論に至りました。暗黙知の事例としては、たとえば、そのプロジェクトの中だけで使われている特殊な専門用語や言い回し、お客さまに合わせたコミュニケーション方法などが挙げられます。
また、ちょうどその頃はNRI社内でもエンゲージメントに関する考え方が変わり始め、「メンバー全員がいきいきと働いている状態を維持できれば組織は活性化する」ということが浸透し始めている時期でもありました。
それ以降、私は、キャリア入社の方をはじめとするさまざまな人たちが集まる組織・プロジェクトチームにおいて、「あらゆる情報がオープンにされている状態をつくること」「オープンなコミュニケーションを取り合うことで相互に信頼し合える状態をつくること」という二つのポイントを重視した組織運営を心掛けるようになりました。その後、2022年の5月頃に初めて坂田さんと出会うことになります。
周囲の人たちに遠慮なく質問できる、心理的安全性が担保された組織
――プロジェクト開始後、和田さんはどのようなことを考えて坂田さんをアサインしましたか?
和田:坂田さんとはそれまで一緒に仕事をしたことがなく、NRIでのキャリアも浅かったので、最初から幅広い領域を見てもらおうとは考えていませんでした。まずは比較的限定的な領域にアサインし、ちょっと様子を見ようと思ったのが最初の状態ですね。
――坂田さんは和田さんから最初にアサインされた仕事について、どのように感じていましたか?
坂田:和田さんのグループに入る以前に担当したエンハンスやマルチリージョンのプロジェクトも前職に比べると十分大きかったのですが、和田さんのプロジェクトはさらに規模が大きいと感じましたし、メンバー各自が見なければならない業務範囲も広かったです。和田さんが「限定的な領域」と話したように、確かに大規模なシステムの限られた範囲ではあるのですが、私としては「一人ひとりがこんなに広い範囲を見るのか」と驚いたことを覚えています。

――その後、和田さんはプロジェクトでの坂田さんの働きぶりをどのように見ていましたか?
和田:坂田さんのプロジェクト内での仕事については、進め方が非常にしっかりしていて、任せたことを着実にやり遂げるスキルやコミットメント力を持っていることがわかりました。これは私だけの意見ではなく、直属のチームリーダーや周囲のメンバーも坂田さんに対して同じような印象を持っていました。
それだけでなく、坂田さんは、自分から積極的に行動してコミュニケーションが取れるタイプで、周囲の心理的安全性の確保までも担ってくれ、チームリーダーとしても十分にやっていけると感じていました。今後も引き続き、視野の広い考え方を身に付けながら、マネジメント範囲を少しずつ広げ、大きなプロジェクトのマネージャーを務められるような人材に成長してほしいと期待しています。
――坂田さんは、どのようなことを意識して仕事を進めていましたか?
坂田:和田さんが冒頭にお話ししたような暗黙知的な情報・ノウハウは、今回のプロジェクトに関しても少なからず散見されました。だからこそ「自分は今までこうやってきた。たぶん、今回もこのやり方で大丈夫だろう」とは考えずに、少しでも不確かなことがあれば、遠慮せずに上司や先輩、周囲のメンバーを巻き込み、確認を取りながら、着実にプロジェクトを推進するように心掛けていました。このような動きが取れたのも、「あらゆる情報がオープンにされている状態」「オープンなコミュニケーションを取り合うことで相互に信頼し合える状態」が、しっかりと浸透した心理的安全性の高い組織であることが大きかったのだと思います。
また、プロジェクトの初期フェーズはメンバーとして参加しましたが、中盤以降はチームリーダーとして最大7名のメンバーとともに仕事をするようになりました。その際、若手メンバーに対しては、「自分の判断だけで進めず、必ずお客さまとの合意を取ることや、周囲のメンバーと確認を取り合うことを徹底しよう」と発信するなど、自分が若い頃にした失敗を伝えることも含め、さまざまな形でコミュニケーションを取りながら、若手メンバーの成長をサポートするようにしています。
新しくプロジェクトに入るキャリア入社の方には必ずメンターを付けている
――坂田さんはNRIに入って以降、会社・上司・先輩・グループなどから受けたサポートの中で、どのようなものが良かったと感じていますか?
坂田:和田さんのグループに入る以前の話になりますが、入社後2カ月程度の助走期間については、どんなことでも気軽に聞けるメンターの先輩が付くなど、さまざまな形での手厚いサポートがあったので、本当にありがたいと思いました。このような新たにジョインするメンバーにメンターを付ける取り組みは、今の和田さんのグループのプロジェクトでもしっかりと行われています。キャリア入社の方たちが不安を感じている時期に、彼らの声の届く距離にいることが重要だと思いますし、私自身もそのような先輩やメンターがいてくれたことで助けられたと感じています。
――プロジェクト単位でもしっかりとメンターを付けているのですね。
和田:そうですね。新しくプロジェクトに入るキャリア入社の社員に関しては、必ずメンターを付けるようにしています。メンターのような「人」のサポートがあることで、最初のハードルはかなり緩和されるはずですからね。また、メンターに関しては、プロジェクトや本人の稼働状況に関係なく、気軽に質問しやすいよう、相性も意識しながらアサインするようにしています。
――坂田さんは、これからNRIでどのようなキャリアを歩んでいきたいですか?
坂田:NRIに入ってすぐに大きなプロジェクトにアサインされ、わずか数年でチームリーダーになれるとは想像もしていませんでした。そのような意味では、入社前に考えていた以上の経験ができていますし、自分なりに成長しているとも感じています。今後も引き続き、期待に応えられるように、マネージャーとして活躍できる実力を身に付け、責任を持ってプロジェクトを動かせる人間に成長していきたいですね。
―― 和田さん、坂田さん、今日はありがとうございました。